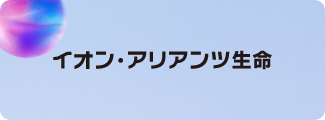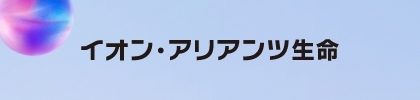お金が貯まらない人が頻繁に訪れる5つの場所
<この記事を読んでわかること>
・「コンビニ」「100円ショップ・ディスカウントショップ」「セール・バーゲン」「食べ放題・飲み放題の店」「宝くじ売り場」に頻繁に行く人はお金が貯まらない可能性がある
・お金が貯まる人は支出を「見える化」している。そのうえ、価値基準が明確で貯蓄を仕組み化している
特に無駄遣いしていないけど「お金がなかなか貯まらない」という人はたくさんいます。でも、日々の行動をチェックしてみると、お金が貯まっている人があまり行かない場所でお金を使っていることがよくあります。そこで今回は、お金が貯まらない人が頻繁に訪れている5つの場所をご紹介。お金の貯まる人と貯まらない人の違いをチェックしておきましょう。
お金が貯まらない人が頻繁に訪れる場所1:コンビニ
コンビニは24時間営業していて、いつでも必要なものが揃っているので便利ですよね。新商品や期間限定の商品などもすぐに店先に並ぶので魅力的。ついあれこれと買ってしまいがちです。
ただ、コンビニに行って、そうやってちょこちょこと買い物している人はお金が貯まりません。
お金が貯まらない人は、支出に気を配らずになんとなくお金を使ってしまいます。このような出費を「ラテマネー」といいます。たとえば、週3日、毎回500円のコーヒーを飲んでいたら、1か月でざっと6000円、1年で7万2000円もの出費になってしまいます。
コンビニのちょこちょこ買いの費用も同様です。1回ずつの買い物は少額でも、それが重なることでお金が貯まらなくなってしまいます。
また、最近はコンビニでもPB(プライベートブランド)の商品を扱ったり、賞味期限が近くなったものを値下げしたりしている場合もありますが、全体的に見るとやはりスーパーより割高です。食品はもちろん、生活用品までコンビニで買うようにすると、お金は貯まっていきません。
お金が貯まる人は、そもそもコンビニに立ち寄らないようにしています。必要なものはなるべくスーパーで揃えるようにして、生活費を押さえています。どうしても今コンビニで買わなければならない、という場合にはコンビニにも行きますが、必要なものだけを買うようにいています。「とりあえずコンビニ」という人は要注意です。
お金が貯まらない人が頻繁に訪れる場所2:100円ショップ・ディスカウントショップ
100円ショップにいくと、「これも100円で買えるの?」と驚くような品物が売っています。家事や生活に役立つアイディアグッズもいろいろあり、使ってみたくなります。
また、ディスカウントショップでは大容量の品物が売られています。「まとめ買いはお得」などと書かれていて、少量の品物よりも単価でみれば安く買うことができます。
確かにお得そうなのですが、100円ショップの品のなかには耐久性に不安のあるものも。短期間で買い換えればいいのかもしれませんが、結局最初から長持ちするものを買ったほうが費用面でも使い心地の面でも満足するでしょう。アイディアグッズも、最初はおもしろがって使うのですが、すぐに使わなくなってあとは保管するだけ…となっては無駄になってしまいます。
また、たとえば「鶏肉3kg」などと大容量の品を買ってきても、食べ切れずに処分してしまうようでは損ですし、何よりもったいないですね。
お金が貯まる人は、100円ショップやディスカウントショップに行かないわけではありませんが、買うものをよく吟味して、本当に必要なもの、使い切れる物だけを選んで買うようにしています。「安いから」などと、値段だけで買い物をした経験のある人は注意が必要です。
お金が貯まらない人が頻繁に訪れる場所3:セール・バーゲン
セールやバーゲンが大好きな人もいるでしょう。高級なブランド品が数十%割引で買えたら嬉しいのはわかります。年末年始、夏ごろ、最近ではブラックフライデーなどでもセールやバーゲンが盛り上がっています。
ただ、セールやバーゲンの商品には、自分の欲しい商品がないケースがほとんど。型落ちの品だったり、少し流行から外れていたりしていて、自分が使えないケースが多いのです。無理やり使っても、あまり満足度は高くないでしょう。となれば、安く買えたとしても損になってしまいます。
そのことを知っているので、お金の貯まる人はセールやバーゲンにはあまり積極的には行きません。ブランド品などを買わないわけではありませんが、値段が安いから買うのではなく、「本当に欲しい」「自分に必要」だから買います。たとえ定価であっても、自分が大きな満足を得られるのであれば買います。
また、お金の貯まる人はセールやバーゲンに行かないことで時間の節約ができます。セールやバーゲンは確かに楽しいかもしれませんが、そのための時間や労力を他のことに注いで時間を無駄にしないようにしています。
お金が貯まらない人が頻繁に訪れる場所4:食べ放題・飲み放題の店
食べ放題・飲み放題の店は、時間内に好きなだけ料理や飲み物を楽しめて人気です。よく「元を取れる?」などといって、腹十二分目まで食べたという話を聞きますが、そこは食べ放題・飲み放題の店もビジネスですから、まず元を取ることができないようになっています。それに、そこまで食べたり飲んだりして体を壊し、病院に行くようでは本末転倒です。
それに、食べ放題・飲み放題では、飲食が中心になってしまい、一緒に行った人とコミュニケーションを取る時間がおろそかになってしまいます。
ですからお金が貯まる人は、あまり食べ放題・飲み放題の店には行きません。食べ放題・飲み放題よりも、自分の食べたい量・飲みたい量だけ注文したほうが満足度の高いことを知っています。また、飲食だけでなく、コミュニケーションも楽しむことで、その後の関係をよりよいものにしていくのです。
お金が貯まらない人が頻繁に訪れる場所5:宝くじ売り場
宝くじには、夢がありますよね。「1等◯億円」などと言われたら、買ってみたくなるものです。宝くじ公式サイトによると、2023年度(令和5年度)の宝くじの販売実績額は8088億円。多くの方が一攫千金の夢を買っていることがわかります。
宝くじは、買わなければ当たらないのはそのとおりです。しかし、買ってもまず当たらないのも事実です。宝くじの当選確率は非常に低く、元をとることさえ困難です。
先の宝くじ公式サイトによると、販売実績額のうち当せん金として支払われている金額は3780億円(46.7%)と、50%にも届きません。これは、宝くじについて定めた「当せん金付証票法」で「当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額をこえてはならない」となっていることによります。そもそも、50%を超えてはいけないのです。
お金の貯まる人はそのことを知っているので、宝くじを買わないか、買うにしても予算を決めて楽しめる範囲で買うようにします。そして、宝くじのような運に頼るのではなく、地道に努力してお金を貯めています。
お金の貯まる人と貯まらない人はどう違う?
お金が貯まらない人が頻繁に訪れる場所を5つ紹介してきました。これらからわかる、お金の貯まる人と貯まらない人の違いをまとめると、次のようになります。
支出を「見える化」し、予算を立てて家計運営している
お金の貯まる人は、支出を「見える化」し、予算を立てています。たとえ毎月の収入が少なくても、支出を減らしていくことで、お金は確実に増えます。そうして、徐々にお金を貯めていくのです。
一方、お金の貯まらない人は支出が見えていないので、予算を気にせず使ってしまう傾向にあります。「これいいな」と思ったらすぐに買ってしまうような人は、要注意です。
支出の価値基準が明確
お金が貯まる人は、自分たちにとって価値があるものにしかお金を使いません。他人が評価するものよりも、自分たちにとって本当に必要なものや大切なものにお金を使います。ですから、無駄遣いをしなくてすみます。
また、目先の楽しみだけを重視してお金を使うのではなく、「今お金を使うことで将来どうなるか」を考えてお金を使います。お金を使うことに常に意識を向けています。
お金の貯まらない人は「せっかくだから」と、買うことが多くあります。安いから、期間限定だから、ここでしか買えないから…と、明確な支出の価値基準がなく、理由をつけて衝動的にお金を使っているならば、改めたほうがよいでしょう。
貯蓄を仕組み化している
お金の貯まる人は、先に貯蓄分を確保して、残ったお金で生活する「先取り貯蓄」をしています。こうすれば、残ったお金をたとえすべて使ったとしても貯蓄分は残すことができます。お金は、あればあるだけ使ってしまうもの。イギリスの歴史学者・政治学者、パーキンソン氏が提唱した「パーキンソンの法則」でも、「支出の額は、収入の額に達するまで膨張する」といわれています。先取り貯蓄は、これに対抗できる方法なのです。
お金が貯まらない人は、「後から貯蓄」「余ったら貯蓄」をしようとしています。「後から貯蓄」では、お金が残らなかったら貯蓄することはできません。先取り貯蓄を取り入れましょう。そして、財形貯蓄や銀行の自動定期積立など、先取り貯蓄を仕組み化できるとさらに有効です。
もし、お金が貯まらない人の行く場所に行くことが習慣になっていたり、お金が貯まらない人の考え方が身についていたりしたら、今回の記事を参考にできることから改善していきましょう。少しずつでも改善することで、お金が貯まらない人からお金が貯まる人へと変わることができるでしょう。

高山 一恵(たかやま かずえ)
Money&You 取締役/ファイナンシャルプランナー
慶應義塾大学卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設⽴。10年間取締役を務めたのち、現職へ。全国で講演活動、多くのメディアで執筆活動、相談業務を⾏ない、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。明るく親しみやすい性格を活かした解説や講演には定評がある。著書は『はじめての資産運用』(宝島社)、『はじめてのNISA&iDeCo』(成美堂)、『税制優遇のおいしいいただき方』(きんざい)など多数。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。