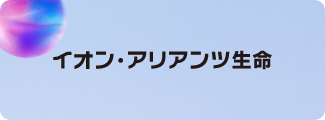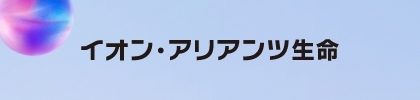マイホームvs賃貸、どちらにすべき?メリット・デメリットを踏まえお金のプロがアドバイス
「マイホームを購入するか、賃貸住まいにするか」。誰もが将来の生活を考えるときに必ず出てくる、永遠のテーマともいえる問題です。自分に合っているのは、マイホームと賃貸のどちらなのでしょうか。
今回は、マイホームと賃貸のメリット・デメリットと、マイホーム購入と賃貸住まいそれぞれでかかる費用の試算を紹介します。
【マイホーム購入のメリット・デメリットは?】
マイホームを購入した場合と、賃貸住まいの場合のメリット・デメリットは、次の表のとおりです。
マイホーム購入と賃貸住まいのメリット・デメリット
| マイホーム購入 | 賃貸住まい | |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
(株)Money&You作成
マイホーム購入のメリット1:住宅ローン返済後は住居費がかからない
マイホームはほとんどの場合、住宅ローンを利用して購入するでしょう。住宅ローンを完済すれば、以後は住居費がかからなくなります。住居費を支払わなくても引き続きそこに住み続けられる点は安心でしょう。
マイホーム購入のメリット2:マイホームが自分の資産になる
住宅ローンを完済すれば、家と土地は自分の資産になります。また、万が一住宅ローンの返済中に亡くなるなどの事態があった場合には、「団体信用生命保険」によって住宅ローンが完済されるため、家族に家や土地を確実に遺すことができます。
マイホーム購入のメリット3:リフォームや間取り変更が自由にできる
マイホームはもちろん自分の家なので、住みやすい間取りやこだわった内装にするなど、自由にリフォームができます。老後に備えて、バリアフリーを重視した住宅にする、といったことも可能です。
マイホーム購入のメリット4:設備のグレードが高い
物件によっても異なりますが、マイホームは同等の広さ・間取りの賃貸住宅よりも設備のグレードが高くなっています。より快適な生活ができるでしょう。
マイホーム購入のデメリット1:転勤などがあっても住み替えしにくい
マイホームを買うと、そこから移動しにくくなってしまいます。遠方に転勤になった、親と同居することになったなど、急にライフスタイルが変わった場合に、マイホームをどうするかという問題が生じます。
マイホーム購入のデメリット2:固定資産税などの税金や管理費・修繕積立金、リフォーム費用が発生する
住居費は毎月の住宅ローンの返済だけではありません。住宅ローンを完済したとしても、固定資産税などの税金はかかります。分譲マンションの場合、毎月の管理費や修繕積立金もかかります。また、長くマイホームに住み続けていれば、家が古くなってきたり、設備が壊れたりすることも。そうしたときのリフォーム費用も発生します。
マイホーム購入のデメリット3:築年数が経過すると資産価値が落ちる可能性がある
マイホームが古くなれば、資産価値はどうしても落ちてしまいます。何かの都合で家を売却せざるを得ないときに、住宅ローンの残りの金額(残債)よりも高く売れないと、家を売っても住宅ローンだけが残る、という事態もあり得ます。
賃貸住まいのメリット・デメリット
一方、賃貸住まいにもメリット・デメリットはあります。
賃貸住まいのメリット1:ライフスタイルや家族構成に合わせて住むエリアや間取りを変えられる
独身のときは費用を抑えてコンパクトな家に住み、結婚して子どもが生まれたら多少広い家に引っ越し。さらに転勤に合わせて会社の近くに移住し、老後は夫婦で住む郊外の小さな家を借りる…などという具合に、住むエリアや間取りを自由に変更できます。
賃貸住まいのメリット2:古くなったら新しい物件に住み替えができ、リフォーム費用も不要
賃貸住宅は、大家さんが建物や設備の管理を行うため、自分でリフォームする必要がありません。古くなってきたと思えば、引っ越して新しい物件に住むこともできます。
賃貸住まいのメリット3:住宅ローンを組まなくてすむ
賃貸住宅を借りるにあたって住宅ローンを組む必要はありません。買った家に不測の事態が起き、「家がなくなって借金だけが残ってしまった…」となることもありません。また、マイホームではかかる固定資産税も、賃貸住まいならかかりません。
賃貸住まいのデメリット1:家賃を払い続けても自分の資産にはならない
賃貸住宅に何年住んでも、自分の資産にはなりません。収入が減る老後も家賃がかかり続け、家計の大きな負担になってしまう可能性もあります。
賃貸住まいのデメリット2:2年ごとに更新料が必要
賃貸では、毎月の家賃とは別に、2年ごとに更新料がかかります。更新料は地域や物件により異なりますが、おおよそ家賃の1〜2カ月分です。収入の少なくなる老後にも更新料はかかりますので、家計の大きな負担になってしまう可能性もあります。
賃貸住まいのデメリット3:高齢になると借りられる物件の選択肢が狭まる可能性がある
高齢になり、健康面のリスクが高い場合や収入が少ない場合、借りられる物件が少なくなる可能性があります。
マイホームと賃貸、かかる金額はどのくらい違う?
マイホームと賃貸にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、どちらを選ぶか迷ってしまうことも多いでしょう。では、金額面ではどうでしょうか。マイホームと賃貸でかかる金額の試算を紹介します。
マイホーム購入vs賃貸住まいシミュレーション
30歳夫婦が90歳まで生きると仮定してシミュレーション:
【マイホーム購入の主な前提条件】
- ・5000万円の一戸建てを購入(頭金として500万円用意)
- ・住宅ローンは変動金利で0.475%、35年返済、ボーナス加算なし
- ・住宅ローン控除は新築・省エネ適合住宅購入で13年間適用される
- ・購入の20年後に小規模なリフォーム、35年後に大規模なリフォームを行う
【賃貸住まいの主な前提条件】
- ・1年目〜6年目は家賃8万円の賃貸住宅に住む
- ・7年目〜24年目の子育て期間は家賃11万円の賃貸住宅に住む
- ・25年目以降は夫婦2人で住むため引っ越しで家をダウンサイジング。家賃8万円の賃貸住宅に住む
| 購入 | 賃貸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,391万円 | 7,504万円 | ||||||
| 一戸建て購入 | 1→6年 | 7→24年 | 25年→ | ||||
| 子育て期間 | 子供独立 | ||||||
| 価格 | 5,000万円 | 敷金(家賃1カ月) | 8万円 | 敷金(家賃1カ月) | 11万円 | 敷金(家賃1カ月) | 8万円 |
| 頭金 | 500万円 | 礼金(家賃1カ月) | 8万円 | 礼金(家賃1カ月) | 11万円 | 礼金(家賃1カ月) | 8万円 |
| 諸費用(物件価格の3%) | 150万円 | 仲介手数料(家賃1カ月) | 8万円 | 仲介手数料(家賃1カ月) | 11万円 | 仲介手数料(家賃1カ月) | 8万円 |
| 毎月返済額(借入条件:変動金利0.475%、 35年返済、ボーナス時加算なし) |
11.65万円 | 家賃 | 8万円 | 家賃 | 11万円 | 家賃 | 8万円 |
| 固定資産税 | 12万円 | 管理費(家賃の10%) | 0.8万円 | 管理費(家賃の10%) | 1万円 | 管理費(家賃の10%) | 0.8万円 |
| 機構団信特約料(3大疾病保障付き)総額 | 453万円 | 更新料(2年に1度) | 8万円 | 更新料(2年に1度) | 11万円 | 更新料(2年に1度) | 8万円 |
| 修繕費用 | 600万円 | - | - | 引っ越し費用 | 15万円 | 引っ越し費用 | 15万円 |
| リフォーム費用(20年後) | 100万円 | - | - | - | - | - | - |
| リフォーム費用(35年後) | 300万円 | - | - | - | - | - | - |
| 住宅ローン控除総額 住居費用より差し引く |
327万円 | - | - | - | - | - | - |
(株)Money&You作成
細かい条件などは物件や地域などにより結果は変わってきてしまうので、あくまでも目安ですが、このケースで試算をすると、賃貸住まいよりマイホーム購入のほうが約100万円安くなります。
ただ、結果が変わらないなら「マイホームを買った方がいい」と考えるのは早いでしょう。
今回の試算では、マイホーム購入のときに頭金を500万円用意しています。もし頭金がなければ、その分住宅ローンの金額を増やさなくてはならず、毎月の返済額は増えます。また、住宅ローンの変動金利が今後上昇した場合、利息負担が増えて返済額が増えることになる点にも注意が必要です。固定金利で住宅ローンを借りれば、将来の金利上昇による影響はありませんが、固定金利は変動金利より金利が高いため、上の試算よりも返済総額は増えることになります。
つまり、金額面でマイホーム購入と賃貸住まいを比較しても、どちらがいいか結論づけるような根拠にならないということです。
マイホームは出口戦略を踏まえて購入しよう
マイホームと賃貸はそれぞれ一長一短あります。金額面の違いも大きな差にはなりづらいです。よって、みなさんがどちらを希望するか、どのように生きたいかというモノサシで選ぶことが大切です。
なお、マイホームを購入する場合には注意点があります。
それは、出口戦略を描ける物件なのかです。仮に住み続けられなくなったというときに、人に「貸す」・「売却する」という選択ができるような家であれば、ライフイベントに対応しやすくなります。支払っている住宅ローンの金額を上回る金額で貸せたり、住宅ローンの残高を上回った金額で売却できたりする物件であれば、万が一住めなくなったときにも安心です。
また、住宅の購入にあたって、会社が住宅手当を支給してくれるようならば、その分支出の負担も減り、購入のメリットが大きくなります。会社によって、住宅手当の有無や金額は異なりますので、詳しくは勤務先にご確認ください。
賃貸住まいで支出をなるべく抑えたい場合は、郊外に移住するのもひとつの方法です。今はリモートワークも浸透し、郊外に移住しやすくなっています。ただ、老後まで踏まえて家を借りるならば、なるべく公共交通機関が整った「都市部の郊外」のような地域を選びましょう。いわゆる車社会の地域だと、高齢になって車が使えないとなったときに、生活が不便になってしまうからです。高齢になっても便利な郊外に注目して移住することで、住居費を下げつつ、交通や買い物の利便性も確保できるでしょう。
マイホームを選ぶにしても、賃貸を選ぶにしても、先々のことを考えた場合には、より支出が減り、お金を貯められる選択をしたいものです。できる限りシミュレーションして「これでいい」と満足できる選択ができるようにしましょう。

頼藤 太希(よりふじ たいき)
マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki