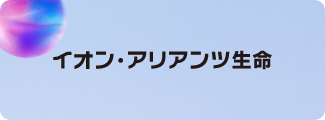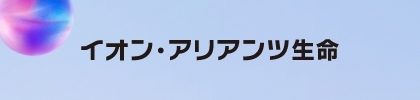障害福祉サービスが利用できる人は?
受けられるサービスの一覧と利用者負担額、利用の流れ
公的保険制度のひとつに「障害福祉サービス」があります。障害福祉サービスは、障害があるために、日常生活や社会生活が困難になっている方の支援を行う制度です。今回は、障害福祉サービスで受けられるサービスの内容を一覧でご紹介。合わせて、障害福祉サービスの利用者負担額や障害福祉サービスの利用の流れについて解説します。
障害福祉サービスはどんな制度?
2013年(平成25年)に施行された「障害者総合支援法」は、障害のある方が地域社会で不自由なく日常生活や社会生活を送ることができるようにするための支援を定めた法律です。障害福祉サービスは、この障害者総合支援法に基づいて提供されるサービスです。
障害福祉サービスには、大きく分けて介護に関するサービスを受ける際に給付が受けられる「介護給付」と、日常生活や就労などに必要な訓練を受ける際に給付が受けられる「訓練等給付」の2つがあります。
障害福祉サービスの対象となる人は、
・身体に障害のある方(身体障害者手帳を交付されている方)
・知的障害のある方
・精神障害(発達障害を含む)
・難病患者等で一定の障害のある方
となっています。また、実際に受ける障害福祉サービスの内容によって、対象者となる条件が細かく定められています。
介護給付・訓練等給付で受けられるサービスを一覧で紹介
介護給付・訓練等給付で受けられるサービスは多岐にわたります。ここでは、主な障害福祉サービスとその内容を紹介します。
| 介護給付 | 訪問系 | 居宅介護 |
|---|---|---|
| 重度訪問介護 | ||
| 同行援護 | ||
| 行動援護 | ||
| 重度障害者等包括支援 | ||
| 日中活動系 | 短期入所 | |
| 療養介護 | ||
| 生活介護 | ||
| 施設系 | 施設入所支援 | |
| 訓練等給付 | 居住支援系 | 自立生活援助 |
| 共同生活援助 | ||
| 訓練系・就労系 | 自立訓練(機能訓練) | |
| 自立訓練(生活訓練) | ||
| 就労移行支援(A型) | ||
| 就労継続支援(B型) | ||
| 就労定着支援 |
厚生労働省のウェブサイトより(株)Money&You作成
介護給付の主な内容
介護給付は、介護に重点を置いたサービスの給付を行う制度です。主に「訪問系」「日中活動系」「施設系」のサービスに分かれています。
【訪問系】
・居宅介護
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事の介護など、生活全般の援助を行います。
・重度訪問介護
重度の肢体不自由・知的障害・精神障害があるなどで常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事の介護・外出時の移動支援などを総合的に行い、在宅生活が続けられるようにサポートします。
・同行援護
視覚障害で移動が困難な人が外出するときに同行して、移動に必要な情報を提供したり、介護したりします。単に行きたいところに行くだけでなく、外出先で不便がないように支援を行います。
・行動援護
行動が困難な知的障害や精神障害のある方が行動するときに、危険を回避するための支援を行います。また、外出時の生活支援も行います。
・重度障害者等包括支援
常時介護の必要な方のなかでも、とくに介護が必要な人に対して、居宅介護や同行援護、行動援護などの複数のサービスを包括的に行います。
【日中活動系】
・短期入所
自宅で介護する人が病気になるなどして介護ができないときに、障害のある方に施設に入所してもらい、生活に必要な介護を行います。
・療養介護
常時介護のほかに医療的なケアが必要な障害のある方に対して、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護・日常生活のサポートを行います。
・生活介護
障害者支援施設などで常に介護を必要とする方に対して、生活の介護等を行うとともに、創作的活動・生産活動の機会を提供します。
【施設系】
・施設入所支援
障害者支援施設などに入所する方に対して、主に夜間や休日に、生活に必要な介護を行います。
訓練等給付の主な内容
訓練等給付は、障害のある方が日常生活や社会生活を送るために必要な訓練を行うサービスです。主に「居住支援系」「訓練系・就労系」に分かれています。
【居住支援系】
・自立生活援助
障害者支援施設を利用していた人が一人暮らしをする際に、自立した日常生活・社会生活を送るために必要な訓練を行います。
・共同生活援助
障害のある方が共同生活を行う住居で生活する際の援助を行います。
・自立訓練(生活訓練・機能訓練)
自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。生活訓練は知的障害や精神障害のある方が対象。機能訓練は身体障害のある方や難病をわずらう方などが対象です。
・就労継続支援(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。A型は雇用型といって、知識や能力が高まった場合、最終的には雇用されることを目指します。B型は非雇用型といって、知識や能力を高めてA型への移行、または雇用を目指します。
・就労定着支援
障害のある方が就労したあとに、長く働き続けられるように生活面などの支援を行います。
障害福祉サービスの利用者負担額は?
障害福祉サービスは、原則として自己負担1割で受けることができます。ただし、毎月の自己負担には、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。1カ月間に利用したサービスの量が多くても、この負担上限月額以上の負担はありません。
障害福祉サービスの利用者負担額
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 (3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯) |
0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯・所得割16万円未満 (収入がおおむね670万円以下の世帯) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(「一般2」になります) |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
厚生労働省のウェブサイトより(株)Money&You作成
所得を判断するときの世帯の範囲は、
・18歳以上の障害者(施設に入所する18歳・19歳を除く)…障害のある方とその配偶者
・18歳未満の障害児(施設に入所する18歳・19歳を含む)…保護者の属する住民基本台帳での世帯
となっています。
生活保護受給世帯や、市町村民税非課税世帯は、障害福祉サービスを自己負担なく受けることができます。また、それ以上の収入のある世帯でも、負担上限月額が決まっているので、かかる費用を大きく抑えることができます。
また、このほかにもさまざまな負担軽減措置が用意されています。
医療型個別減免
療養介護を利用する場合、福祉サービスの自己負担額と医療費、食事療養費を合算して上限額を設定します。20歳以上の入所者で低所得の人は、少なくとも25,000円が手元に残るように利用者負担額が減免されます。
高額障害福祉サービス等給付費
障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険の負担額も含む)が上限額を超えた場合には、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。
食費等実費負担の減免措置
入所施設の食費・光熱水費の実費負担の上限は54,000円ですが、低所得者に対する給付については、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
グループホームの利用者への家賃助成
グループホームの利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃は、利用者1人当たり月額1万円(1万円未満の場合は実費)を上限に補足給付が行われます。
生活保護への移行防止
これらの負担軽減を行なっても生活保護の対象となってしまう場合、生活保護の対象にならない額まで自己負担の上限額や食費などの実費負担額が引き下げられます。
障害福祉サービスを利用するには?
障害福祉サービスの利用手続きは、市区町村の窓口で行います。役所の「障害福祉課」「保健福祉課」などで問い合わせると良いでしょう。
障害福祉サービスの利用までの流れは、介護給付と訓練給付で異なります。
介護給付ではまず、心身の状況に関する調査や医師の意見書などをもとに、障害支援区分の認定が行われます。認定が行われたら、サービス等利用計画案を作成します。サービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者と相談して作成するのが一般的です。そして支給決定後、介護サービスを受けることができるようになります。
訓練給付には「障害支援区分の認定」のプロセスがありません。サービス等利用計画案を作成、提出し、支給決定後に職業訓練などを受けることができるようになります。
障害福祉サービスの手続きに必要なものは、次のとおりです。
・障害者手帳
・支給申請書兼利用負担額減額の免除申請書(窓口でもらって記入)
・所得調査同意書(窓口でもらって記入)
・障害年金等の金額がわかるもの(振込通知書など)
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(障害者は本人のもの、障害児は本人及び保護者のもの)
自治体によっては、この他にも必要なものがある場合があるので、事前に窓口に確認しておくとスムーズです。
障害福祉サービスは障害があるために、日常生活や社会生活が困難になった方の支援を行う制度。介護給付・訓練等給付を通して、障害のある方の日常生活・社会生活をサポートしてくれます。
ただ、厚生労働省「障害福祉分野の最近の動向」によると、障害者の総数964.7万人のうち障害福祉サービスを利用しているのは障害者95万人、障害児42.4万人にとどまっています(令和3年10月時点)。もしも障害福祉サービスの対象になるのであれば、家計の大きな助けになることは間違いありませんので、ぜひ活用を検討してみてください。

高山 一恵(たかやま かずえ)
Money&You 取締役/ファイナンシャルプランナー
慶應義塾大学卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設⽴。10年間取締役を務めたのち、現職へ。全国で講演活動、多くのメディアで執筆活動、相談業務を⾏ない、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。明るく親しみやすい性格を活かした解説や講演には定評がある。著書は『はじめての資産運用』(宝島社)、『はじめてのNISA&iDeCo』(成美堂)、『税制優遇のおいしいいただき方』(きんざい)など多数。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。