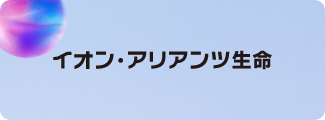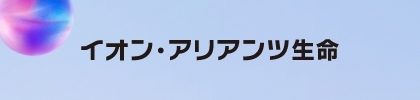自立支援医療の対象疾患は?
3つのタイプと受給者証の申請・更新の方法を紹介
日常生活のさまざまなリスクに備える公的保険制度のひとつに、心身に障害を負った方が利用できる「自立支援医療」があります。自立支援医療を利用すると、医療費の自己負担額を軽減することができます。今回は、自立支援医療の概要と3つのタイプ、自立支援医療の対象となる疾患や軽減額まで、自立支援医療について詳しく解説します。
自立支援医療の3つのタイプ 対象となる疾患は?
自立支援医療は、心身の障害の除去や治療にかかる医療費を給付する制度です。心身の障害の治療は長期に及ぶことも多く、医療費がいくら原則3割負担だといっても自己負担が大きくなってしまいがちです。自立支援医療を利用することで、その負担を減らし、治療に専念できるようになるというわけです。
自立支援医療には、大きく3つのタイプがあります。
自立支援医療のタイプ1:精神通院医療
精神通院医療は、精神疾患を抱えていて、通院による治療を続ける必要のある方の医療費の自己負担を軽減する制度です。
精神通院医療の対象となる精神疾患は、てんかんを含む何らかの精神疾患です。厚生労働省のウェブサイトによると、
1.病状性を含む器質性精神障害
2.精神作用物質使用による精神および行動の障害
3.統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
4.気分障害
5.てんかん
6.神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
7.生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
8.成人の人格および行動の障害
9.精神遅滞
10.心理的発達の障害
11.小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害
(1〜5は「重度かつ継続」(後述)に該当)
があげられています。いずれも、通院による治療が必要な程度の状態の方が対象になります。また、症状がほとんどない状態であっても、再発を予防するために通院が必要ならば精神通院治療の対象になります。
自立支援医療のタイプ2:更生医療
更生医療は、身体障害を抱えている(身体障害者手帳を持っている)満18歳以上の方が、その障害を除去・軽減する治療を受けるときの医療費の自己負担を軽減する制度です。
更生医療の対象となる障害は、多岐にわたります。
更生医療の対象となる障害と標準的な治療の例
| 障害 | 治療の例 |
|---|---|
| 視覚障害 | 白内障の水晶体摘出手術など |
| 聴覚障害 | 鼓膜穿孔の閉鎖術など |
| 言語障害 | 外傷性・手術後に生じる発音構語障害の治療など |
| 肢体不自由 | 人工関節置換術など |
| 内部障害 | (心臓)ペースメーカー埋込み手術など |
| (腎臓)人工透析療法など | |
| (肝臓)肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など | |
| (小腸)中心静脈栄養法など | |
| (免疫)HIV感染症に対する治療など |
厚生労働省のウェブサイトより(株)Money&You作成
更生医療では、これらの治療によって確実に効果が見込まれるものに対して、医療費が支払われます。
自立支援医療のタイプ3:育成医療
育成医療は、18歳未満の障害を持つ子ども、または将来障害が残ると認められる疾患を持つ子どもが、その障害を除去・軽減する治療を受けるときの医療費の自己負担を軽減する制度です。
育成医療の対象となる障害も、更生医療と同様で多岐にわたります。
育成医療の対象となる障害と標準的な治療の例
| 障害 | 治療の例 |
|---|---|
| 視覚障害 | 白内障、先天性緑内障の治療など |
| 聴覚障害 | 先天性耳奇形の治療など |
| 言語障害 | 口蓋裂の治療など |
| 肢体不自由 | 先天性股関節脱臼の治療など |
| 内部障害 | (心臓)ペースメーカー埋込み手術など |
| (腎臓)人工透析療法など | |
| (肝臓)肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など | |
| (小腸)中心静脈栄養法など | |
| (免疫)HIV感染症に対する治療など | |
| (その他)先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症などの外科手術など |
厚生労働省のウェブサイトより(株)Money&You作成
育成医療でも、これらの治療によって確実に効果が見込まれるものに対して、医療費が支払われます。
自立支援医療の負担上限額は?
公的医療保険の場合、医療機関や薬局などにかかった場合の医療費の自己負担額は通常3割ですが、自立支援医療を利用すれば、自己負担額を原則1割にすることができます。たとえば、1カ月の医療費が1万円の場合、通常の3割負担ならば3,000円ですが、自立支援医療の適用を受ければ1割負担で1,000円にできます。
また、「1割負担」が大きくなりすぎないように、自立支援医療では世帯の所得による1カ月あたりの上限が設けられています。
その上、医療費が高額な治療を長期間受ける必要がある「重度かつ継続」に該当する方は、さらに別の負担上限月額が定められており、負担が軽減されます。
重度かつ継続に該当するのは、次のいずれかの方です。
・医療保険で高額療養費の支給を直近12カ月の間に4回以上受けた「多数回該当」の方
・次の1〜5の精神疾患の方
1.病状性を含む器質性精神障害
2.精神作用物質使用による精神および行動の障害
3.統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
4.気分障害
5.てんかん
・3年以上精神医療を経験している医師から、入院によらない計画的・集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方
所得区分別の自己負担の上限額は、次のとおりです。
所得区分別の自己負担の上限額
| 所得区分(医療保険の世帯範囲) | 更生医療・精神通院医療 | 育成医療 | 重度かつ継続 | |
|---|---|---|---|---|
| 一定所得以上 | 市町村民税235,000円以上 (年収約833万円以上) |
対象外 | 対象外 | 20,000円 |
| 中間所得2 | 市町村民税33,000円以上235,000円未満 (年収約400~833万円未満) |
総医療費の1割又は 高額療養費(医療保険)の 自己負担限度額 |
10,000円 | 10,000円 |
| 中間所得1 | 市町村民税33,000円未満 (年収約290~400万円未満) |
5,000円 | 5,000円 | |
| 低所得2 | 市町村民税非課税 (低所得1を除く) |
5,000円 | ||
| 低所得1 | 市町村民税非課税 (本人又は障害児の保護者の年収80万円以下) |
2,500円 | ||
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | ||
※年収については夫婦+障害者である子の3人世帯の粗い試算
厚生労働省のウェブサイトより(株)Money&You作成
たとえば、精神通院医療の適用をうけた「低所得2」の方が病院・薬局にかかり、1カ月の医療費が10万円かかったとします。このとき、本来の自己負担額は3割負担で3万円ですが、精神通院医療の適用を受けているので、自己負担額は1割負担の1万円です。さらに、上の表をみると低所得2の方の自己負担の上限額は5,000円ですので、実際の自己負担は5,000円になるというわけです。
自己負担の上限額は、所得が増えるほど多くなります。ただ、「一定所得以上」であっても、医療費は1割負担となる点は変わりません。
なお、「重度かつ継続の一定所得以上」の区分と「育成医療の中間所得」の区分は、当初2021年(令和3年)3月31日までの経過的特例とされていましたが、2024年(令和6年)3月31日まで、3年間延長されています。2024年4月以降、経過的特例が終了した場合は、この区分に該当する方は自己負担の上限がなくなる(対象外になる)ことになります。
自立支援医療の受給者証はどうすればもらえる?
自立支援医療の給付を受けるには、「自立支援医療受給者証」が必要です。
自立支援医療受給者証の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。役所の「障害福祉課」「保健福祉課」などで聞いてみましょう。
自立支援医療受給者証を申請するときには、次のものを用意しましょう。なお、自治体によって他にも必要なものがある場合もあるので、詳しくはお住まいの市区町村でご確認ください。
自立支援医療支給認定申請書
自立支援医療の申請書は市区町村の役所にあります(医療機関にある場合もあります)。その場で記載して提出したいならば、印鑑を忘れずに持っていきましょう。
医師の診断書
医師の診断書は通院している医療機関で書いてもらいます。事前に医療機関に伝えて、用意してもらいましょう。なお、「重度かつ継続」に当てはまる場合は診断書の様式が異なる場合もあります。
世帯の所得の状況が確認できる資料
住民税課税世帯の場合は課税証明書、住民税非課税世帯の場合は非課税証明書が必要です。生活保護世帯の場合は、生活保護受給証明書を提出します。これらの証明書は市区町村で入手できます。また、住民税非課税世帯の場合は、本人確認書類も一緒に提出します。
健康保険証
健康保険証は写しでも問題ありません。
マイナンバーの確認書類
いわゆるマイナンバーカードなど、マイナンバー(個人番号)のわかる書類も必要です。
その他、自治体によっては必要書類が異なる場合があるため、あらかじめ担当課や地域の保健福祉センターなどに問い合わせておくと良いでしょう。
申請が認められると、自立支援医療受給者証が交付されます。自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票を医療機関に提示すれば、自立支援医療が受けられます。
ただし、自立支援医療が受けられる医療機関は、自治体が定める「指定自立支援医療機関」で、受給者証に記載されたところに限られます。指定自立支援医療機関でない医療機関や、受給者証に記載のない医療機関では自立支援医療を受けられません。
また、自立支援医療受給者証の有効期限は1年間で、引き続き利用する場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは、有効期間終了の3カ月前から受付が始まります、詳しくは申請した市町村にご確認ください。
自立支援医療は、心身の障害の治療にかかる医療費の負担を軽減してくれる制度です。医療費が3割負担から1割負担になるうえ、所得によっては医療費が上限額までで済む場合もあります。利用にあたっては申請が必要なので、該当する場合はぜひ手続きをしておきましょう。

高山 一恵(たかやま かずえ)
Money&You 取締役/ファイナンシャルプランナー
慶應義塾大学卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設⽴。10年間取締役を務めたのち、現職へ。全国で講演活動、多くのメディアで執筆活動、相談業務を⾏ない、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。明るく親しみやすい性格を活かした解説や講演には定評がある。著書は『はじめての資産運用』(宝島社)、『はじめてのNISA&iDeCo』(成美堂)、『税制優遇のおいしいいただき方』(きんざい)など多数。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。