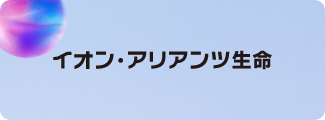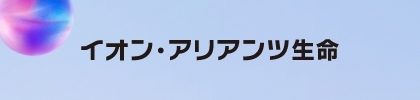保険は掛け捨て型? それとも貯蓄型? どちらを選ぶべき?
日本では、生命保険に加入する人がたくさんいます。生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(2021年度)によると、個人年金保険を含む民間の生命保険の世帯加入率は89.8%にのぼります。ただ、ちゃんと仕組みを理解して加入している人は、少ないかもしれません。今回は、保険の種類としてよく言われる「掛け捨て型」と「貯蓄型」の違いをご紹介します。
掛け捨て型とはどんな保険?
掛け捨て型の保険は、万が一のときの保障だけを用意する保険です。
そもそも保険は、みんなで保険料を出し合って備えるしくみになっています。保険料を出した誰かに万が一のことが起きたら保障を行うものです。掛け捨て型の保険は、そのしくみをシンプルに活用できる保険です。
掛け捨て型の保険では、保険を途中で解約したときの「解約返戻金」や、保険が満期を迎えたときの「満期保険金」はないか、あってもごくわずかです。保険の保障期間中に保険の対象となる被保険者が亡くなったり、所定の病気やケガの状態になったりしたときには保障が受けられますが、そうした事態がなかった場合は、支払った保険料は「掛け捨て」になります。
「掛け捨て」というと、何だかもったいなく感じられるかもしれませんが、通常、次に説明する貯蓄型の保険よりも保険料が安くなります。
掛け捨て型の主な保険には、定期保険・収入保障保険・一般的な医療保険・一般的ながん保険などがあります。
定期保険
定期保険は、死亡・高度障害時に保険金が受け取れる保険です。少額で大きな保障が得られるのが特徴です。
収入保障保険
収入保障保険は、被保険者が死亡または高度障害になったときに、年金形式でお金が受け取れる保険です。保険期間が進むほど保険金の総額が減っていきます。
医療保険
医療保険は、被保険者が所定の病気やケガになった場合にお金が受け取れる保険です。公的な医療保険の保障を補う形で利用されます。なお、貯蓄型の医療保険もあります。
がん保険
がん保険は、がんにかかった場合に保障が受けられる保険です。多くのがん保険では、がんと診断された場合に診断一時金を受け取れます。また通院時の治療費や働けないときの生活費を保障したり、医療機関などに相談できるセカンドオピニオンサービスを用意したりしているがん保険もあります。なお、貯蓄型のがん保険もあります。
貯蓄型とはどんな保険?
一方、貯蓄型の保険は、万が一のとき以外にもお金がもらえる保険です。
貯蓄型の保険は、掛け捨て型の保険とは違い、途中で解約したときには解約返戻金、満期を迎えたときには満期保険金が受け取れます。もちろん、万が一のときにもお金が受け取れます。つまり、保障と貯蓄を一緒に用意できるというわけです。保険料は掛け捨て型より高くなるのが一般的ですが、お金を強制的に貯めていくことができます。
貯蓄型の主な保険には、終身保険・養老保険・学資保険・個人年金保険などがあります。
終身保険
終身保険は、保障が一生涯続く保険です。定期保険では、保険の保障期間が終わったあとに万が一のことがあっても、保険金は受け取れません。しかし、終身保険ならば亡くなるまで保障が続くので、解約しない限り遺族は必ず死亡保険金を受け取れます。
養老保険
養老保険は、保険の保障期間中に亡くなった場合には死亡保険金、満期を迎えた場合には満期保険金が受け取れる保険です。死亡保険金と満期保険金は基本的に同額です。満期保険金を受け取ると、そこで保険の契約は終了します。
学資保険
学資保険は、子どもの教育費を用意するための保険です。子どもが大学進学を迎える18歳などまでの間保険料を支払うことで、満期になったときにお金が受け取れます。高校などの入学時に「祝い金」としてお金を一部受け取れる保険もあります。満期になる前に契約者が亡くなった場合、その後の保険料の支払いは免除され、子どもが18歳になったときなどにお金が受け取れるため、教育費を確実に用意することができます。
個人年金保険
個人年金保険は、保険料を60歳・65歳といった年齢まで支払うことで、契約時に定めた年齢に達したあとに年金形式でお金を受け取れる保険です。年金の上乗せを用意できます。なお、保険料払込期間中に亡くなった場合は、遺族が死亡給付金を受け取れます。
生命保険の基本形は「定期保険」「終身保険」「養老保険」の3つです。ここまでお話しした内容をもとにまとめると、次のようになります。
保険のしくみ
【定期保険・終身保険・養老保険の比較】
| 定期保険 | 終身保険 | 養老保険 | |
|---|---|---|---|
| 保険期間 | 一定期間(期間満了まで) | 一生涯 | 一定期間(満期まで) |
| 解約返戻金 | なし(あってもわずか) | あり | あり |
| 満期保険金 | なし | なし | あり |
| 保険料 | 終身保険・養老保険より安い | 養老保険より安い | 定期保険・終身保険より高い |
| メリット | ・安価な保険料で保障を用意できる | ・亡くなるまで保障が続く ・解約返戻金を受け取れる |
・解約返戻金・満期保険金が受け取れる |
| デメリット | ・中途解約したり満期を迎えたりしたりしてもお金は受け取れない | ・保険料が定期保険より高くなる ・中途解約の場合、解約返戻金が元本割れすることがある |
・保険料が定期保険・終身保険より高くなる ・中途解約の場合、解約返戻金が元本割れすることがある |
(株)Money&You作成
掛け捨て型と貯蓄型、保障を用意するならどっち?
掛け捨て型と貯蓄型の生命保険の違いを見てきましたが、ここで本来の保険の役割を思い出してみましょう。
保険の役割は、「もしものときにお金で困ることに備える」ことです。
たとえば、一家の大黒柱が亡くなったとき、遺された家族が十分生活していけるほどの貯蓄があれば、なにも保険を利用する必要はありません。お金で困らないからです。しかし、貯蓄がまったくなかったり、あっても少なかったりしたら、遺された家族は生活に困ってしまいます。こんなとき、保険に加入していれば、貯蓄がまったくなかったとしても、家族に保険金が支払われるため、家族がお金で困ることをなくせます。
貯蓄がないときの保障を用意したいのですから、保険料はなるべく安く抑えたいでしょう。
では、その他の保険、特に貯蓄型の保険は不要なのかというと、そうではありません。確かに貯蓄型の保険は、掛け捨て型の保険と比べると保険料が高くなります。また、貯蓄型の保険の予定利率(保険会社が運用するときに約束する利率)は近年下落していて、昔ほどは大きくお金が増えなくなっています。
しかし、貯蓄型の保険では、もしものときの保障を用意しながら将来に向けてお金を貯めることができます。保険料が掛け捨てにならないのは貯蓄型の保険のメリットです。
また、貯蓄型の保険はお金を貯めたり管理したりすることに自信のない方にも向いています。貯蓄型の保険を利用すれば、普段からお金のやりくりを気にしなくても、毎月決まった額の保険料が自動的に引き落とされて、保障を用意しつつお金を貯めることができます。貯蓄型の保険では、お金を先取りで強制的・自動的に貯めることができるのです。
そのうえ、貯蓄型の保険の貯蓄部分は、銀行の普通預金などとは違って簡単に引き出すことはできません。「ちょっと今月はお金を使っちゃおう」などと、つい預貯金などから引き出して使った経験のある方でも、お金を確実に貯められるでしょう。
ただし、貯蓄型の保険の解約返戻金は、解約の時期によっては支払った保険料の総額を下回ってしまうことがあります。特に早期に解約するほど、元本割れする可能性がありますので、利用にあたっては解約の必要がないように、余裕を持って取り組むことをおすすめします。
まとめ
掛け捨て型の保険と貯蓄型の保険の特徴の違いを解説してきました。もしものときの保障は定期保険や終身保険で用意するのがおすすめですが、お金を貯めたり管理したりすることに自信がないならば貯蓄型保険にもメリットがあります。家計や加入中の保険を見直して、自分に合った保険を選びましょう。

頼藤 太希(よりふじ たいき)
マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki