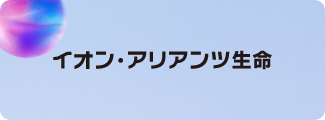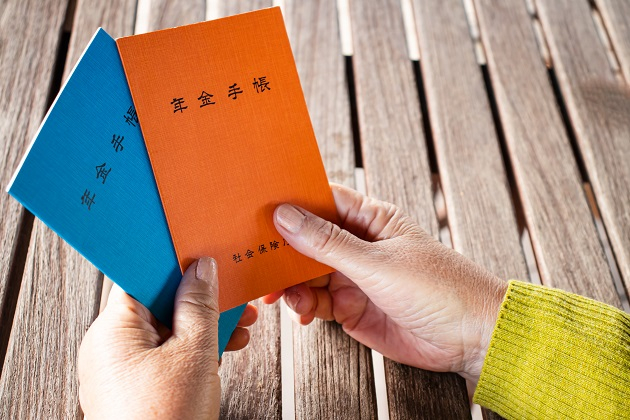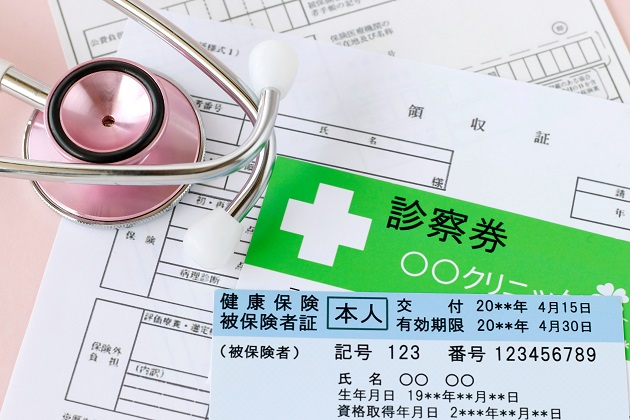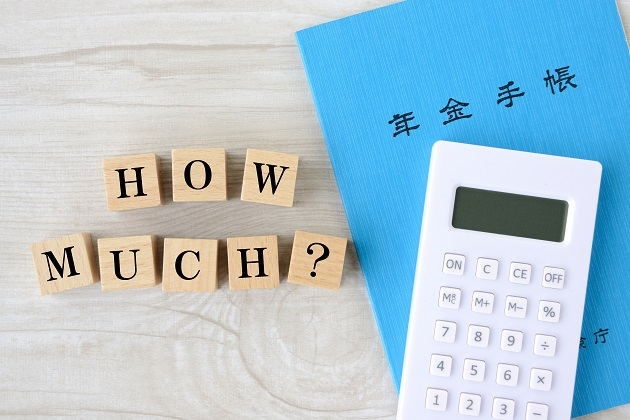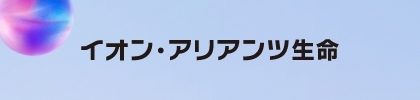公的保険はどんなものがある?
種類やしくみを解説
ケガ・病気・失業・障害・老齢・介護……。私たちの生活には、さまざまなリスクがあります。このリスクに備えるための保険には、大きくわけて公的保険と民間保険の2種類があります。
今回は公的保険にスポットを当ててご紹介。公的保険の種類やしくみ、公的保険からもらえる主な給付について解説します。
国や自治体が守ってくれる公的保険
保険には、公的保険と民間保険の2種類があります。
公的保険は国や自治体が運営する保険です。公的保険では、加入の対象になった場合には、原則として強制的に加入します。つまり、公的保険は、国や自治体が守ってくれる保険といえます。なお、公的保険の保険料や保障の内容はあらかじめ決まっています。
一方の民間保険は保険会社が運営する保険です。公的保険と違って、民間保険は加入する・しないを自分で選べます。民間保険は、公的保険に上乗せする保障を用意できる保険といえます。民間保険はどんな保障を用意するかを自分で選ぶため、保障の内容も保険料も人それぞれ異なります。
7種類ある公的保険
公的保険はさらに7種類にわけることができます。
【公的保険の概要と主な給付の種類】
| 保険の種類 | 内容 | 主な給付 |
|---|---|---|
| 公的医療保険 | 業務外のケガや病気をした場合の保障や給付、出産や子育てなどの際の給付を行う | ・療養の給付 ・高額療養費 ・傷病手当金 ・出産育児一時金 ・出産手当金 ・埋葬料 ・児童手当 など |
| 労災保険 | 業務上のケガや病気をした場合の保障や給付を行う | ・休業補償給付 ・療養補償給付 ・遺族補償年金 ・疾病補償年金 ・障害補償給付 ・介護補償給付 ・葬祭料 など |
| 公的年金 | 高齢・障害・死亡などの際に保障や給付を行う | ・老齢基礎年金 ・老齢厚生年金 ・障害基礎年金 ・障害厚生年金 ・遺族年金 ・寡婦年金 ・死亡一時金 ・中高齢寡婦加算 など |
| 公的介護保険 | 介護が必要になった人への保障や給付を行う | ・予防給付 ・介護給付 など |
| 雇用保険 | 失業した場合などの保障や給付、再就職に向けての給付を行う | ・基本給付(失業保険) ・就職促進給付 ・教育訓練給付 ・雇用継続給付 など |
| 自立支援医療 | 心身の障害にかかわる医療を受けるときに給付を行う | ・精神通院医療 ・更生医療 ・育成医療 |
| 障害福祉サービス | 障害のある人が介護を受けたり、社会生活に必要な能力の訓練を受けたりするときに給付を行う | ・介護給付 ・訓練等給付 |
株式会社Money&You作成
公的保険にどんなものがあるのか、どんな給付が受けられるのか簡単に紹介します。
公的保険1:公的医療保険
公的医療保険は、業務外のケガや病気の治療にかかる医療費の負担を軽減する保険です。日本では「国民皆保険」といって、すべての人が必ず公的医療保険に加入する必要があります。
公的医療保険には、会社員や公務員などとその扶養家族が加入する健康保険と、自営業者や個人事業主、フリーランス、無職の人などが加入する国民健康保険があります。また、原則75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度に加入します。
病院や薬局などで保険証を提示すると、医療費の自己負担が原則3割になります。これは、公的医療保険があるおかげです(療養の給付)。そのほかにも、主に次のような給付が受けられます。
〇高額療養費制度
1カ月間(各月1日〜末日)の医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が一定の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。たとえば、年収約370万円〜770万円(70歳未満)の人の場合、自己負担限度額は約9万円。たとえ1カ月間に100万円の医療費がかかったとしても、窓口で支払う金額はまず3割負担で30万円になり、さらに高額療養費制度が適用されて約21万円が戻ってきます。
〇傷病手当金
健康保険に加入している人が、業務外のケガや病気で仕事を休んだ場合に受け取れるお金です。通算して1年6カ月の間、給料のおよそ3分の2のお金が受け取れます。なお、傷病手当金は原則として健康保険の加入者しかもらえません。
〇医療費助成制度
公的医療保険からは、ほかにもさまざまな医療費の助成が受けられます。たとえば、一定年齢に達するまでの子どもの医療費を助成する「乳幼児医療費助成制度」や「義務教育就学医療助成制度」、ひとり親の医療費を助成する「ひとり親医療費助成制度」、指定の難病にかかり医療機関にかかる際の医療費を助成する「指定難病医療費助成制度」などがあります。自治体により制度の有無や内容、名称は異なります。
公的保険2:労災保険
労災保険は、仕事中や通勤中の事故によってケガ・病気・障害・死亡といった被害を受けたときに給付が受けられる保険です。よく「労災」と略されていますが、正しくは「労働者災害補償保険」といいます。医療機関にかかる際には療養補償給付、仕事を休むことになったら休業補償給付、障害を負ったら障害補償給付という具合に、さまざまな補償が用意されています。
労災保険は、正社員のような正規雇用でも、パートやアルバイトのような非正規雇用でも、労働者を1人でも雇用している事業者はすべて加入しなければなりません。また保険料も、事業者がすべて負担します。
公的保険3:公的年金
日本の公的年金には、国民年金と厚生年金があります。国民年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入する年金です。一方の厚生年金は、会社員や公務員が勤務先を通じて加入する年金です。
年金というと、老後に受け取るお金を連想する方が多いでしょう。確かにそのとおりで、65歳になると国民年金・厚生年金から老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取ることができます。しかし、それだけではありません。被保険者がケガや病気で所定の障害状態になったときには障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)、被保険者が亡くなったときにはその方によって生計を維持されていた遺族が遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)を受け取ることができます。
公的保険4:公的介護保険
公的介護保険は、介護が必要になったときに所定の介護サービスを受けることができる保険です。40歳になると公的介護保険に全員加入し、介護保険料を支払います。
65歳以上の人は「第1号被保険者」、40〜64歳の人は「第2号被保険者」となります。第1号被保険者は、要介護状態になった原因を問わず公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者は、加齢に起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り介護サービスを受けることができます。
公的介護保険では、要介護認定を受けることで、原則1割負担で介護サービスが受けられます。また、介護費用が高額な場合は、「高額介護サービス費」や「高額介護合算療養費制度」を利用すると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。また、介護する方にも「介護休業給付」という給付金が用意されており、家族などが介護するために休業した場合に、お金を受け取ることが可能です。
公的保険5:雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行って、労働者の生活や雇用の安定を図る制度です。労働時間が週20時間以上で、31日以上雇用される見込みの労働者は、雇用保険に必ず加入しなくてはなりません。
雇用保険の給付には、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類があります。もっともよく知られているのは、求職者給付に該当する「失業手当」「失業保険」などと呼ばれることもある基本手当でしょう。次の仕事を探す間に退職前の賃金日額の45~80%を90日〜360日間もらうことができます。基本手当の受け取れる日数は年齢や雇用保険の加入期間、退職理由により異なりますが、次の仕事がみつかるまでの大きな助けになるでしょう。
また、公共職業訓練などを受講する場合には「技能習得手当」、早期に再就職できた場合には「再就職手当」、スキルを磨くための教育訓練を受ける場合には「教育訓練給付金」という具合に、さまざまな給付を受けることができます。
公的保険6:自立支援医療
自立支援医療は、心身の障害の除去や治療にかかる医療費を給付する制度です。公的医療保険の場合、医療費の自己負担額は通常3割ですが、自立支援医療では自己負担額を原則1割にすることが可能です。所得が一定額未満の場合や症状が重度の場合はさらに負担を減らすことができます。
自立支援医療には、統合失調症などの精神疾患をサポートする「精神通院医療」、身体障害者手帳の交付を受けた人の治療を支援する「更生医療」、18歳未満の人の障害の治療を応援する「育成医療」の3種類があります。
公的保険7:障害福祉サービス
障害福祉サービスは、身体障害や精神障害を抱える方が社会のなかで暮らしやすくなるように支援を行うサービスです。日常生活の訓練などを支援する「訓練等給付」、日常生活に必要な介護を支援する「介護給付」があります。訓練等給付、介護給付ともさまざまなメニューが用意されています。
まとめ
公的保険の種類としくみを解説してきました。公的保険は充実していることがお分かりいただけるでしょう。公的保険は、日常生活のリスクに対処するのに役立ちます。もし、自分が保障や給付金を受けられる対象になったならば、忘れずに申請しましょう。

高山 一恵(たかやま かずえ)
Money&You 取締役/ファイナンシャルプランナー
慶應義塾大学卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設⽴。10年間取締役を務めたのち、現職へ。全国で講演活動、多くのメディアで執筆活動、相談業務を⾏ない、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。明るく親しみやすい性格を活かした解説や講演には定評がある。著書は『はじめての資産運用』(宝島社)、『はじめてのNISA&iDeCo』(成美堂)、『税制優遇のおいしいいただき方』(きんざい)など多数。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。