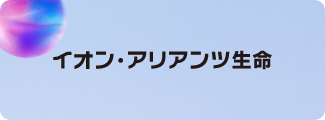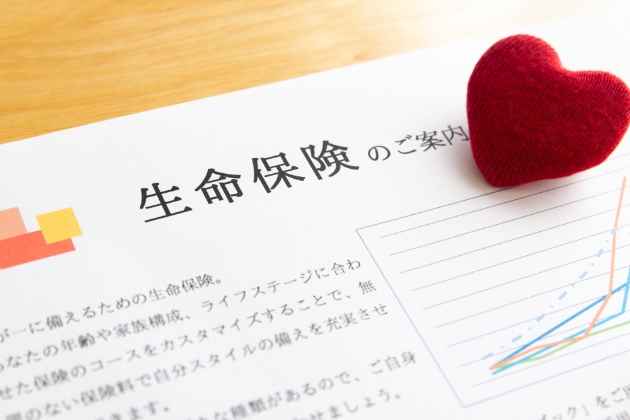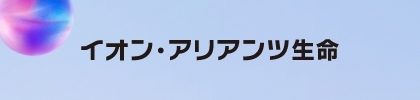ふるさと納税は自己負担2000円で返礼品がもらえるお得な制度!
全国の自治体に寄付ができる「ふるさと納税」。ふるさと納税は、寄付をすることで自治体を応援できるうえ、自己負担2,000円で各地域の返礼品(お礼の品)がもらえるうれしい制度なのですが、「まだふるさと納税をしたことがない」という方もいるかもしれません。
そこで今回は、ふるさと納税のしくみやメリットをご紹介。まだふるさと納税をしたことない方、今年こそはスタートしましょう!
寄付すると返礼品がもらえるふるさと納税
ふるさと納税は、全国の自治体の中から、自分の選んだ自治体に寄付をする制度です。寄付をすることで、各地域の返礼品が受け取れます。また、2,000円を超えた分については、寄附金控除を利用することで所得税や住民税を安くできます。つまり、実質2,000円の自己負担だけで、返礼品が手に入るというわけです。
ふるさと納税をするときには、ふるさと納税の専用サイトを利用するのが便利です。ふるさと納税の専用サイトでは、全国の自治体の返礼品をジャンル別・寄付額別などで検索できます。その中から、気に入った返礼品を選んで手続きすれば、簡単に寄付ができます。なお、「ふるさと」という名前がついていますが、自分の故郷や関わりの深い地域を選ぶ必要はありません。ですから、自分の好きな自治体に寄付をすればいいでしょう。
ふるさと納税で寄附金控除をするには、確定申告をする方法としない方法(ワンストップ特例制度)の2種類があります。具体的な手順は、以下のとおりです。
確定申告をする方法
- ①自治体にふるさと納税の寄付をする
- ②自治体から返礼品と「寄附金受領証明書」が届く
- ③確定申告を行い、寄附金受領証明書を添えて提出する
- →寄付した年の所得税が還付され、翌年度の住民税が安くなる
ワンストップ特例制度を利用する方法
- ①自治体にふるさと納税の寄付をする
- ②ワンストップ特例制度の申請書を提出する
- ③ふるさと納税の納税先とお住まいの自治体間で情報がやりとりされる
- →翌年度の住民税が安くなる
こうして見ると、ふるさと納税はワンストップ特例制度を利用したほうが簡単そうですね。
しかし、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用するには、次の条件を満たす必要があります。
ふるさと納税のワンストップ特例を利用する条件
- ・確定申告をしないこと
- ・1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内であること
ワンストップ特例は確定申告しないことが条件ですから、自営業やフリーランスといった、もともと確定申告が必要な方は使えません。また、会社員や公務員でも、医療費控除や住宅ローン控除がある、あるいは年収が2,000万円を超えているなどで、確定申告を行う場合には利用できません。また、ふるさと納税の寄付先が5自治体を超えると、ワンストップ特例は利用できません。これらの場合は、確定申告を利用しましょう。
なお、確定申告では所得税が還付されて住民税が安くなるのに対し、ワンストップ特例では住民税が安くなるだけです。ただ、安くなる金額の合計はどちらも同じです。ふるさと納税で寄付をしたら、給与明細などで住民税が安くなっているか、確認しましょう。
ふるさと納税の返礼品にはどんなものがある?
ふるさと納税の返礼品は実に多彩です。どの自治体も、自分の自治体にふるさと納税の寄付をしてもらいたいということで、返礼品には力が入っています。
ざっと返礼品のジャンルをあげてみましょう。みなさんは、どんな返礼品がほしいですか?
- ・肉
- ・魚
- ・米
- ・野菜
- ・酒
- ・お菓子
- ・果物
- ・日用品
- ・家電製品
- ・装飾品 など…
ふるさと納税の専用サイトを見ると、ブランドの肉や魚介類、おいしそうな果物やスイーツなどが並んでいます。実際、そうした高級食材であってもふるさと納税ならば自己負担は2,000円で手に入るのですから、人気があります。確かに、普段は口にしないような食材をおいしくゲットするのも、ひとつの考えです。
ただ、そうした高級食材は、もしふるさと納税がなかったら買わなかったのではないでしょうか。ふるさと納税の楽しみとして少しだけもらう分にはまだいいかもしれませんが、全額を高級食材に回すのは、ちょっともったいないかもしれません。
そこで、生活費を削減するために、ふるさと納税の返礼品として、あえて日々の生活で購入しているものをいただくのはいかがでしょうか。 たとえば、日持ちするお米や調味料などを返礼品でもらえば、毎月の食費が削減できます。また、トイレットペーパーやティッシュペーパー、洗剤などを返礼品でもらえば、毎月の消耗品費も減らせます。実際、筆者の自宅にはふるさと納税の返礼品でもらったボックスティッシュがたくさんあります。ずっと買わずに済んでいます。
ふるさと納税の専用サイトで、どんな返礼品があるのかを見るだけでも楽しいものです。ぜひチェックしてみてください。
ふるさと納税でお得になるには?
「そんなにお得なら、できるだけたくさん寄付したい!」と思われる方もいるでしょう。しかし、ふるさと納税で寄附金控除できる金額には上限があります。これを控除額上限といいます。
控除額上限は、ふるさと納税をする人の年収や家族構成などによって異なります。
【ふるさと納税の控除額上限の目安】
(円)
| 寄付した 本人の年収 |
独身または共働き | 夫婦または共働き+子1人 (高校生) |
共働き+子1人 (大学生) |
夫婦+子1人 (高校生) |
共働き+子2人 (大学生+高校生) |
夫婦+子2人 (大学生+高校生) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | - |
| 350万円 | 34,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
| 450万円 | 52,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
| 500万円 | 61,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
| 550万円 | 69,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
| 650万円 | 97,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
※給与収入のみ、住宅ローン控除を受けていない方の場合
総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」より作成
たとえば、年収が400万円の独身の方が寄付する場合、年間の控除額上限はおよそ4万2,000円です。このうち2,000円は自己負担となります。残りの4万円分は寄附金控除をすることで所得税・住民税が安くなります。
ふるさと納税自体は、上限を超えてもできます。しかし、控除額上限以上に寄附金控除を利用して所得税や住民税を安くすることはできません。ですから、ふるさと納税をするにあたっては、自分の控除額上限を調べたうえで、なるべくその上限までふるさと納税を行うのがもっともお得で、おすすめです。
なお、上の表はあくまで参考例ですが、正確な控除額上限は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」で計算できます。「寄付金控除額の計算シミュレーション」を利用して、みなさんの「控除額上限」の目安を算出してみましょう。ふるさと納税の専用サイトでも、同様のシミュレーションが用意されています。
控除額上限を知ったうえで、その上限を超えないようにしつつふるさと納税をしましょう。
まとめ
全国の自治体に寄付をして応援できるふるさと納税のしくみを紹介してきました。自己負担2,000円で各地域の返礼品をいただきながら、所得税や住民税も安くできます。ふるさと納税は2008年からスタートした制度です。すでに10年以上も続いているのに、まだ利用していないのであればもったいない!今年こそぜひふるさと納税に挑戦しましょう。まずは自分の控除限度額を確認し、お得な返礼品を探してみてくださいね。

畠山 憲一(はたけやま けんいち)
Mocha編集長
1979年東京生まれ、埼玉育ち。大学卒業後、経済のことをまったく知らないままマネー本を扱う編集プロダクション・出版社に勤務。そこでゼロから学びつつ⼗余年にわたり書籍・ムック・雑誌記事などの作成に携わる。その経験を生かし、マネー初心者がわからないところ・つまずきやすいところをやさしく解説することを得意にしている。2018年より現職。ファイナンシャル・プランニング技能士2級。教員免許も保有。趣味はランニング。