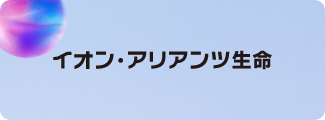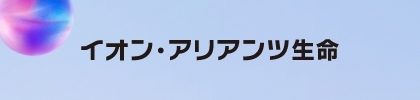年収の壁とは?税法上と社会保険上の扶養はどう違う?
<この記事を読んでわかること>
・年収の壁は税金や社会保険料の負担が増える境目
・2024年・2025年の「年収の壁引き上げ」によって、給与所得控除や基礎控除が増えたほか、大学生年代の「特定親族特別控除(仮称)」も創設された
・手取りに大きな影響を与えるのは106万円の壁・130万円の壁
ニュースでよく話題になる「年収の壁」。「年収の壁を超えないように働き方を調整した」という経験のある方も少なくないのではないでしょうか。年収の壁は、年収に応じていろいろあります。そこで今回は、そもそも年収の壁とは?という基本から、さまざまな年収の壁を超えることで出てくる影響、そして「働き損」にならないようにするための年収はどれくらいなのかを考える上で参考になるようシミュレーションも紹介しています。
なお、家族の形はいろいろありますが、この記事では話をわかりやすくするために、以下「主たる生計維持者」が夫で、妻が夫の扶養に入ってパートで働くという前提で話を進めます。
年収の壁と2種類の扶養
そもそも年収の壁とは、「年収がこの壁を超えると、税金や社会保険料の負担が増えますよ」という境目のことです。妻が専業主婦で夫に扶養されていれば、妻は税金や社会保険料の負担をする必要がありません。
しかし、その妻がパートなどで働き、年収が各種の年収の壁を超えると、扶養から外れて「税金や社会保険料を納めてください」となるわけです。そして、場合によっては、税金や社会保険料を負担することで、年収の壁を超えない範囲で働くよりも手取りが減ってしまう逆転現象が起こることも…。せっかくたくさん働いたのに、「実は働かない方が手取りを多くできた」となるのは、嫌ですよね。
「夫の扶養に入る」という場合の扶養には、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。妻が夫の税法上の扶養から外れると、妻や夫の税金(所得税や住民税)が増加します。それに対して、社会保険上の扶養から外れると、妻が健康保険料・年金保険料・介護保険料などを負担する必要が出てきます。そして、年収の壁によって、税法上の扶養に影響があるのか、社会保険上の扶養に影響があるのかが違います。
扶養に入るための「年収の壁」をチェック
2024年から2025年にかけて年収の壁が大きな話題になりました。物価が上がり、手取りが上がらないなか、年収の壁を引き上げることで税金を減らし、手取りを増やすことが検討されたのです。その結果、2025年時点の主な年収の壁は次のようになりました。
年収の壁1:100万円の「住民税の壁」【税法上の扶養】
100万円の壁は、住民税の壁です。住民税は、お住まいの都道府県・市区町村に支払う税金ですが、原則的には、年収93万円〜100万円を超える人が課税対象になります。
ただし、住民税が非課税となる収入の金額は、お住まいの自治体によって異なりますので、気になる方は確認するようにしましょう。
年収の壁2:106万円の「社会保険の壁」【社会保険上の扶養】
106万円の壁は、社会保険の壁です。妻が次の5つの条件をすべて満たした場合、妻は夫の社会保険上の扶養から外れ、勤め先の社会保険に入ることになります。
①労働時間が週20時間以上
②月収が8万8000円以上(8万8000円×12ヶ月=105万6000円≒106万円)
※月収に残業代や交通費は含まない
③勤務期間が2ヶ月超の見込み
④勤務先の従業員が51人以上
⑤学生ではない
社会保険に入ると、厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料を支払う必要があります。社会保険料は、給与から天引きされます。
106万円の壁は今後撤廃される予定です。賃金の要件(月収が8万8000円以上)は2026年10月になくなり、企業規模(従業員51人以上)も2027年10月になくなる見込みです。労働時間(週20時間以上)の要素は残る見込みで、「労働時間を週20時間未満に抑える」という働き控えが起きることも懸念されています。
年収の壁3:123万円の「所得税の壁」【税法上の扶養】
123万円の壁は、所得税の壁です。これまでは「103万円の壁」でしたが、123万円に引き上げられました。
所得税は、所得に応じて支払う税金ですが、所得からはほぼすべての人が適用できる基礎控除58万円と、金額に応じて給与所得控除を差し引くことができます。給与所得控除の最低金額は65万円となっています。つまり、妻の年収が123万円以下であれば、123万円―58万円(基礎控除)―65万円(給与所得控除)=0となり、所得税はかかりません。しかし、123万円を超えると、所得税がかかるようになります。
加えて、政府は年収850万円以下の人を対象に基礎控除額を上乗せする「基礎控除の特例」を創設しました。これにより、基礎控除の引き上げ額は次のようになります。
基礎控除の特例の引き上げ額は、もっとも多い年収200万円以下で47万円です。この基礎控除の特例により、所得税の年収の壁はもっとも高くて「160万円」(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)となります。年収200万円以下の基礎控除の引き上げは「恒久的な措置」となっています。
基礎控除の特例の引き上げ額は、年収が上がるにしたがって段階的に減りますが、年収200万円超850万円以下の人も所得税が減ります。ただし、年収200万円超850万円以下の人の基礎控除の特例は現状、2年間(2025年・2026年)限定です。2027年以降は基礎控除の特例はなくなります。また、年収850万円超になると基礎控除の特例による引き上げはありません。
少々ややこしいのでまとめると、
・年収200万円以下の人は、所得税の壁が160万円
・年収200万円超850万円以下の人は、基礎控除の特例によって所得税がかかり始める金額が変わる(2025年・2026年限定)。2027年以降は、所得税の壁が123万円
・年収850万円超の人は、所得税の壁が123万円
となります。
年収の壁4:130万円の「社会保険の壁」【社会保険上の扶養】
会社の規模が小さいなどで、106万円の壁の条件を満たさない場合でも、妻の収入が130万円を超えるとすべての人が社会保険に加入することになります。妻は、勤務先の厚生年金、健康保険に加入するか、国民年金、国民健康保険に加入します。
年収の壁5:150万円「特定親族特別控除の壁」【税法上の扶養】
所得控除の1つに、扶養者が受けられる「扶養控除」があります。通常、扶養控除の控除額は所得税38万円・住民税33万円なのですが、大学生年代(19歳〜23歳未満)の子を扶養している場合は「特定扶養控除」といって、所得税63万円・住民税45万円の控除が受けられます。
これまで、子がパート・アルバイトをして年収103万円を超えると、特定扶養控除が受けられなくなってしまっていたのですが、2025年以降は、特定扶養控除の適用対象となる子の年収上限が123万円に引き上げられました。
また、子の年収が123万円を超えた場合、新たに「特定親族特別控除(仮称)」が適用されるようになりました。子の年収が150万円までは、特別扶養控除と同じく63万円の控除が受けられます。子の年収が150万円を超えても、年収188万円まで段階的に控除額が減るようになり、扶養者の手取りが急激に減ることを防ぎます。
年収の壁6:160万円「配偶者特別控除の壁」【税法上の扶養】
妻の給与収入が103万円を超えても、160万円までであれば、夫は別途38万円の「配偶者特別控除」を受けられます。しかし、配偶者特別控除は、妻の給与収入が160万円を超えると徐々に少なくなります。そして、妻の年収が201.6万円を超えると、配偶者特別控除はゼロになります。配偶者特別控除が少なくなったり、ゼロになったりすることで、夫の税金が高くなります。なお、2024年までは「150万円」だったのですが、10万円引き上げられました。
パートで「働き損」にならない年収は?
妻が働き、年収が一定以上になれば、税金や社会保険料がかかるようになるため、手取りが減ってしまいます。とはいえ、税法上の扶養の壁を超える分にはそれほど気にすることはありません。税法上の壁を多少超えても、超えた分にのみ税金がかかるので、増える税額は少額だからです。
むしろ、影響が大きいのは社会保険上の扶養の壁を超えてしまう場合。社会保険料の金額は高額です。つまり、106万円の壁・130万円の壁を超えそうな場合には注意が必要というわけです。以下、簡単に試算してみましょう。
<試算の前提条件>
・夫に扶養されている妻(パート)
・給与所得控除は65万円
・社会保険料は給与収入の15%と仮定
・所得控除は基礎控除(所得税95万円・住民税43万円)と社会保険料控除(社会保険料全額)のみ
・住民税は所得割(課税所得の10%)+均等割(誰もが一律で支払う住民税)5,000円
※復興特別所得税(所得税額の2.1%)は考慮していません
106万円の壁を超えるとどうなる?
条件を満たす会社の場合、給与収入が106万円以上になると勤め先の社会保険に加入します。給与収入が106万円の人の場合、社会保険料や税金は次のようになります。
・社会保険料(給与収入の15%)…106万円×15%=15万9,000円
・所得税…106万円−65万円(給与所得控除)−95万円(基礎控除)−15万9,000円(社会保険料控除)=ゼロ(課税所得がゼロなので非課税)
・住民税(所得割)…106万円−65万円(給与所得控除)−43万円(基礎控除)−15万9,000円(社会保険料控除)=ゼロ(課税所得がゼロなので住民税の所得割は非課税)
・住民税(均等割)…5,000円
このとおり、社会保険料は15万9,000円、住民税は5,000円ですので、給与収入106万円の場合の手取り額は106万円−15万9,000円−5,000円=89万6,000円になります。
それに対して、給与収入が105万円の場合の手取り額はどうなるでしょうか。
・社会保険料(給与収入の15%)…給与収入が106万円未満なのでゼロ
・所得税…105万円−65万円(給与所得控除)−95万円(基礎控除)=ゼロ(課税所得がゼロなので非課税)
・住民税(所得割)…105万円−65万円(給与所得控除)−43万円(基礎控除)=
ゼロ(課税所得がゼロなので非課税)
・住民税(均等割)…5,000円
給与収入105万円から引かれるのは、住民税均等割の5,000円のみ。社会保険料はありません。したがって、給与収入105万円の場合の手取り額は105万円−5,000円=104万5,000円になるのです。
つまり、給与収入が106万円の人は、105万円の人より14万9,000円も手取りが少なくなってしまいます。
130万円の壁を超えるとどうなる?
106万円の壁の条件を満たさなくても、130万円の壁を超えると社会保険料を支払う必要があります。106万円と同様に、130万円の壁の前後で手取りを計算すると、次のようになります。
【給与収入130万円の場合】
・社会保険料…19万5,000円
・所得税…ゼロ
・住民税(所得割+均等割)…7,500円
(税金・社会保険料合計)…20万2,500円
→手取り…130万円−20万2,500円=109万7,500円
【給与収入129万円の場合】
・社会保険料…ゼロ
・所得税…ゼロ
・住民税(所得割+均等割)…2万6,000円
(税金・社会保険料合計)…2万6,000円
→手取り…129万円−2万6,000円=126万4,000円
したがって、給与収入が130万円の人は、129万円の人より16万6,500円も手取りが少なくなってしまいます。
なお、上記はあくまで試算であり、他の条件によっても金額は大きく異なりますので、ひとつの参考までにご覧いただければと思います。
年収の壁を超えて働くのもあり
社会保険上の壁である106万円の壁・130万円の壁を超えると、社会保険に加入することになるため、手取りは確かに大きく減ります。しかし、妻が社会保険に加入すると、老後の年金(厚生年金)が増え、会社を病気やケガで休んだ時には傷病手当金が受け取れ、出産で会社を休んだときには出産手当金を受け取れます。
ですから、可能であれば社会保険上の壁を気にせず、できるだけ働くという選択もありでしょう。働き方を考える際に、ぜひ参考にしてください。

高山 一恵(たかやま かずえ)
Money&You 取締役/ファイナンシャルプランナー
慶應義塾大学卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設⽴。10年間取締役を務めたのち、現職へ。全国で講演活動、多くのメディアで執筆活動、相談業務を⾏ない、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。明るく親しみやすい性格を活かした解説や講演には定評がある。著書は『はじめての資産運用』(宝島社)、『はじめてのNISA&iDeCo』(成美堂)、『税制優遇のおいしいいただき方』(きんざい)など多数。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。